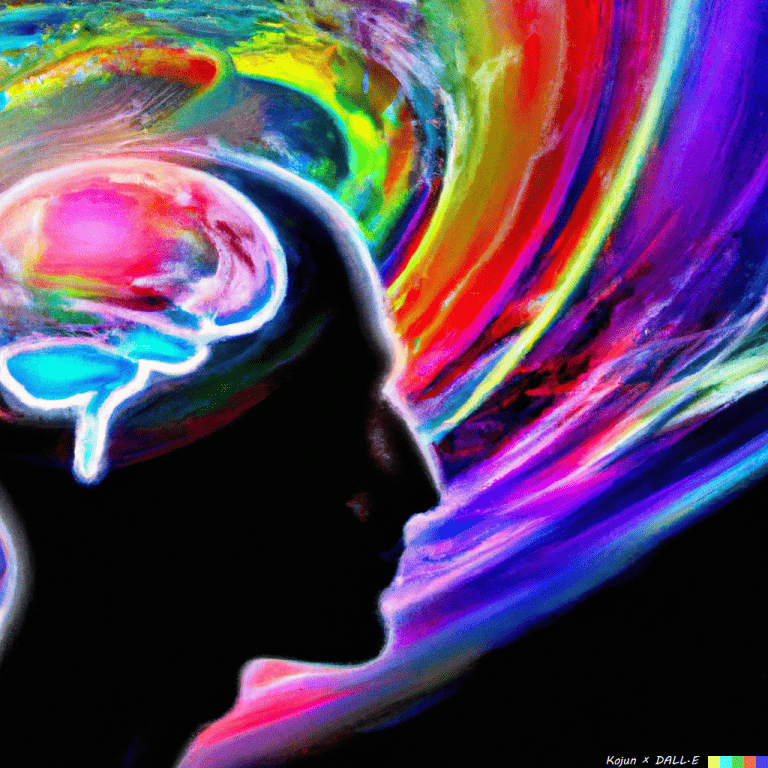食事と睡眠
よくある保健指導
一般的には「食べ過ぎてはいけません」と教えます。しかしまあ、食べ過ぎる人は食べることでストレス解消しようとしていたりするので、「食べるな」という指導は、「いま苦しまないと後でもっと苦しむぞ」というような指導になっています。これはパニッシュメント型動機づけ、つまり罰による教育という形です。それも罪悪感という罰を植え付けるわけです。
で、食べ過ぎる原因のひとつにレプチン(満腹ホルモン)の不足というのがあり、これは睡眠不足によって起こります。そこで、「ちゃんと睡眠をとりなさい。さもなくば太りますよ」と脅します。これもパニッシュメント型動機づけです。
我慢できずにお菓子を食べてしまうときに、「あー、ダメな私」と思うと、「私はダメだから、食べちゃうんだよね」という思考回路が出来てしまいます。そして、自分はダメだという信念を強化しようとします。
心理セラピストである私が保健指導するとしたら、これは避けます。
人の脳は将来の報酬よりも現在の報酬を優先します。それに、罰を与えると、将来の不健康を避けるのではなく、ダイエットや健康改善というゲーム事体から逃げようとします。
心理セラピストKojun流の保健指導
私なら、それよりも、レプチンを強調すると思います。
お菓子を我慢できないときに、「あー、ダメな私」ではなく、「あー、レプチン欲しい」と思ってもらうのです。我慢できないお菓子の誘惑が強ければ強いほど、レプチンの有難さが分かります。
そして、夜、夜更かしせずに、ストレッチでもしてぐっすり眠ればレプチンが手に入るのです。夜更かししてしまったら、「あー、レプチンを貰い損ねた」と思ってもらいます。
これらは報酬型の動機付けです。
しかも、お菓子を食べるときにレプチンが欲しい、寝るときにレプチンが得られる、というようにその瞬間ごとに条件付けられます。お金やポイントが使う瞬間だけでなく貯まる瞬間も嬉しいように。
なんで、食べ過ぎるな、ちゃんと寝ろと言うのに、肝心のレプチンだけ教えないんですかね。
気になる方はグレシンも調べてください。
朝食を食べる
よくある保健指導
「朝食を食べましょう」とも言われます。そこで一般的には理想的な朝食が勧められます。「炭水化物をとりましょう」とか。
朝食と聞いただけで、「あ、僕は朝食べれないんで」と拒絶反応をする人が多いです。これは「頑張って食べなきゃだめですよ」と言われてきたからでしょう。
「朝食」という言葉や概念に対して嫌悪反応が植え付けられています。
心理セラピストKojun流の保健指導
心理セラピストである私はこう言います。「ちゃんとした朝食なんてせずに、牛乳とかバナナとか一口食べればいいんですよ」と。保健師や栄養士に叱られそうですが。
朝食を食べない(単に習慣ではなく食べれないという)人は、朝食べるのがしんどいと思っているのです。ですから、「朝食=しんどい」を解除することが先決です。ですから、楽な朝食を体験してもらう必要があります。
しかも、「ちゃんとした朝食ではない罪悪感」を持ったら負けですから、牛乳やバナナの一口でもメリットがあることを伝えます。「体内時計をリセットするために食べるんですよ。栄養を摂ろうなんて思わないでください」と。また、保健師や栄養士に叱られそうですが。
「それくらいのことで心身が楽になるなら、やらなきゃ損」ってことになるわけです。で、「もっと気持ちいいこと教えてください」となったら、「インスタントのお粥もありますよ」なんて・・・。
心理セラピストは罰を嫌う
まあ、心理セラピストも脅しを使わないわけではありません。だけれども、それは「えいやっ」で乗り越えられるような事柄についてです。意志の力で持続的に本能と闘うなんて、無茶です。すでに負けが続いている場合なんかは特に。
これはスモールステップにしましょうというような単純なことではありません。究極の決断を迫っているわけです。欲望に対して、欲望をデザインしているのです。
支援者にとっての都合のよい成果ではなく、人の幸せに本当に関心がないと答えは見えてこないと思います。