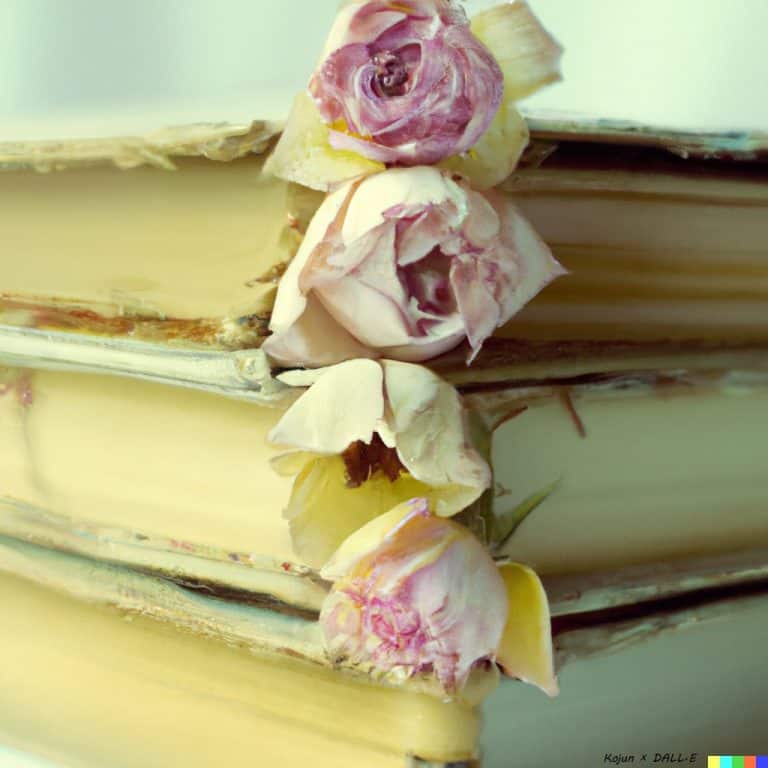よくある誤解について書いておきます。
「よかったー。良いカウンセラーに出会えた」と思ったら、翌日に様々なネガティヴ感情が沸き上がってきて大変なことになることがあります。
また、福祉などの関係者からよく相談されることとして、相談者がホッとすると突然トラウマ反応のようなもの(実はちょっと違う)が出ることがあります。
また、セルフコンパッション(自分を責めるのをやめる)という実践でも、起きることとして知られています。
これらは専門用語で「バックドラフト」と呼ばれているものかと思います。
ですが、この言葉を知った対人支援スタッフや当事者の殆どがその意味を誤解しているのを見かけます。
以下、Kojunの経験からの個人的な定義で説明します。
バックドラフトはトラウマ反応と区別したほうがよい
「バックドラフト」という言葉が普及しはじめていて、聞きかじった人たちから「トリガーされたトラウマ反応」「再トラウマ的なアクシデント」のことだと誤解されているようです。バックドラフトはそれ自体は避けたいものの、失敗や事故というより、むしろ「癒しの兆候」とも呼ばれる現象です。少なくとも「悪化」と誤解すると、その後の進め方の判断を誤ります。
同じ反応である場合もあるのですが、文脈が異なります。あるいは反応の内容が異なります。
トラウマ反応/再体験/メデューサ
トラウマ反応/再体験というのは、トラウマ的な記憶が活性化して、主に恐怖や再体験が生じることです。トラウマ界隈では、ギリシャ神話のメデューサに喩えられます。それは不用意にトラウマに触れ急いだときに起こります。心理セラピーなどでは、少しずつ触れてゆくことでトラウマからの回復が起きるのですが、心理セラピー外でトリガーされると(急ぎすぎたり、安全が整っていないと)と、そのようなことが起こり得ます。
たとえば、マインドフルネスで「内側に注意を向けてください」などと指示されると、トラウマ反応が起きることがあります。それは身体が覚えている「ドキドキ」とか「ビクビク」とかの記憶が活性化されるからです。
ですから、トラウマサバイバーはメデューサが潜んでいるかもしれない内側に意識を向けるのは、そっとそっとやりましょう、ということになります。
バックドラフト
一方で、最初に挙げた、良いカウンセラーとの出会い、相談現場、セルフコンパッション等では、「さあ、そのときのことを話してください」などという誘導はしていないのです。どちらかというと、安心したり、ホッとしたりしているのです。これは、トラウマと向き合うことを急ぎすぎたのではありません。緩んじゃったんです。油断したというとイメージしやすいかもしれません。
バックドラフトは元は消防用語で、燃えている建物の密閉された部屋に扉を開けて新鮮な酸素が一気に入ることで炎が爆発的に大きくなる現象を指します。安心という酸素が入ることで、急激なセラピープロセスが起きてしまう(生きる力、向き合うことの価値が爆発)というイメージです。メデューサではなく、自身の力の解放かもしれないのです。ですから、バックドラフトは癒しのサインでもあるのです。
(ただ、ややこしいですが、安心して緩むことでメデューサが出ることもあります。その場合は、安心して緩んだからだと理解することで再トラウマ予防になるかと思います。という意味で、バックドラフトに準じた扱いでよいかと思っています)
心理セラピーでトラウマを扱っている最中にバックドラフトが起きることは通常ありません。むしろ、心理セラピーの打合せをしているときとか、セラピストと会った翌日に起きたりします。つまり、「あー、いいセラピストを見つけた。これで助かるー」と思うことで起きるのです。恐怖やフリーズが再現されることもありますが、理不尽さへの怒りとか、養育者への残念な気持ちとかが溢れてくること(再体験ではなく、自分を取り戻すための体験)も多いです。それらの感情は、次回のセッションを待たずにフライングでプロセスが進み始めちゃったということです。
トラウマ反応とバックドラフトは似ている面もありますが、区別します。というか、おそらく、トラウマ反応と区別するために「バックドラフト」という言葉があると思ってもよいです。
トラウマ反応は避けるべき道を知らせています。バックドラフトは進むべき道を知らせています。
トラウマ反応はトリガー(きっかけ)を避けることで、防ぐように努めましょう。
一方で、バックドラフトはトリガーを避けることは難しいです。しいていえば、安心や癒しがトリガーなのですから。それは、良いカウンセラー/セラピストに出会ったということであったり、良い実践を習得しはじめたということを意味します。
「バックドラフトの原因と向き合う」などの表現は間違いでしょう。
「○○に意識を向ける実践をしていたら、バックドラフトがでちゃってさあ」などの表現も間違いでしょう。
「それはバックドラフトだから、落ち着いて対処しましょう」ということです。まず、それがトラウマ反応ではなくバックドラフトであることを認識し、静まるのを待ちます。必要なら、グラウンディングなどをしてもいでしょう。
Kojunがずっと悔やんでいること
実はかつてのKojunはバックドラフトという言葉を知らずに、この現象を体験的、暗黙的に知っていました。だって当事者実践家の間ではお馴染みですから。しかし、臨床心理学の学問を勉強をしはじめた頃に「あんなことはしてはいけない」「根拠のあることしかしてはいけない」「勘や暗黙知を使ってはいけない」などの作法を学んでしまい、失敗した時期がありました。
相談段階のクライアントさんにバックドラフトが起きたとき、経験知を使って「それは、安心して蓋が開いただけだと思いますよ」と説明するのを躊躇してしまい、クライアントは怖がってセラピーに進むのを断念してしまいました。そのようなことが2回ほどありました。後にバックドラフトを知り、Kojunの体験知は間違っていなかったことが分かりました。まだ専門知識と擦りあっていなかった当時であっても、「これは私の経験知なですけどね・・・」と前置きして説明すればよかったと悔やんでいます。
その反省から、学術的な根拠のない経験知も、経験知として率直にクライアントに提供することにしました。おもしろいことに、学術的エビデンスのある選択肢と、Kojunの経験知や勘による選択肢を提示したとき、殆どのクライアントがKojunの経験知や勘の方を試してみたいと言います。なんてことだ・・・あの頃、権威に遠慮して率直に自分の意見をクライアントに言わなかったことを申し訳なく思います。
このような経験を重ねて、当事者の知恵を伝えることは、たとえ学術界のべき論から白い目で視られようとも、クライアントの機会を守るためだと思うようになりました。
さらなる注意
バックドラフトは悪いものではない、むしろプロセスの中であり得ること、と説明してきたわけですが、その理解が普及すると今度はバックドラフトが起きて大喜びするという勘違いが予測されます。
「うわあ、バックドラフトですね。よかったですね」、みたいなのもなんだかへんです。昔、「好転反応」という言葉が流行ったときもそうでした。
長年動かなかったものが動き始めたという意味ではよろこばしい面もありますが、もっとイケイケというわけではありませんので。バックドラフトすることでトラウマが回復するというわけではなくて、そこから調整に入ったり、場合によってはタイミングを見直したりは必要です。