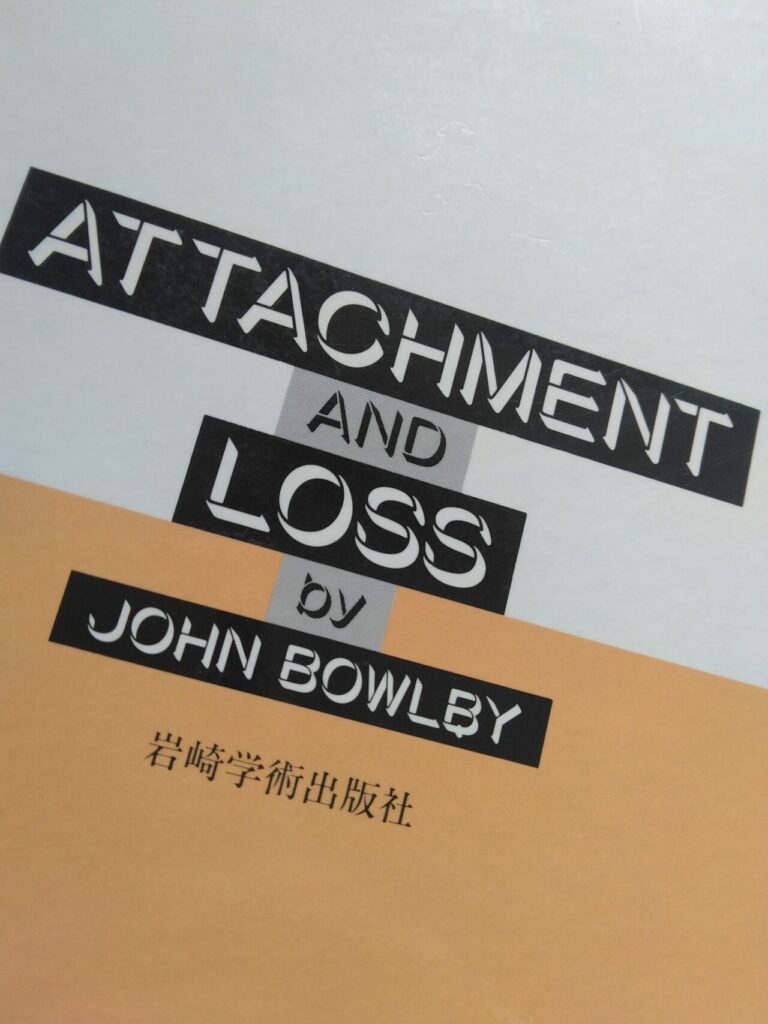心理セラピストKojunが参考にしている文献を紹介します。オススメ本というよりは、世界観の紹介です。
今回のテーマは「愛着」。愛着といえば、子どもを扱う福祉や教育の分野の支援者向けの本が多いですが、興味あるのは人生課題としての愛着の理解のための文献です。ただ、子どもについての文献でも、大人の愛着不安定の人が自分が今挑んでいる段階を理解するのに役立ったりします。
『母子関係の理論』J.ボウルビィ
愛着理論と言えばこれ。ダントツに重要だと思います。
先ず3部作の1冊目で、チンパンジー、ゴリラ、人間の「愛着行動」が観察されています。それは、母親にくっつくという行動のことです。類人猿の研究ですから、愛着というのは、人間の動物(哺乳類・霊長類)としての側面に関わるってことですね。
愛着障害とか愛着不安定とかの悩みや苦しみは愛着スタイルですが、その安定化には言語を使う以前の動物的、おそらく身体感覚かとても大事だろうということが実感されます。
3部作は「愛着行動」に続いて「分離不安」「喪失」と続きます。頼れるものと離れる、安心の基を失うみたいなことが愛着不安定の正体として示唆されます。
それをヒントに実践知を振り返ると、その回復には「安心を得ること」と「離れたり、失ったりしても大丈夫になること」の2つの側面があるように思えてきます。これらの2つは真逆のようでもあり、表裏一体のようでもあります。
愛着不安定の克服には、依存先を見つけることと、依存先からはなれること、両方の体験を楽しむことが鍵となりそうです。
分厚い3部作なので、なかなか一般の方は手に取らないかもしれませんが、殆どの愛着障害に関する書籍の末尾文献リストに挙がっています。原題はずばり『Attachment and Loss』(直訳するなら、愛着と喪失)です。
『子供の「脳」は肌にある 』(山口創)
身体感覚的なものが大事だろうということに、ずばり答えてくれるのがこの本。「愛着」という言葉はタイトルに含まれませんが、読むだけで愛着の克服を導いてくれそうな本です。かつて、愛着サバイバーたちの間で読み継がれていました。
※愛着の文献はなかなか実感に合うものありません。たいていの書籍では、愛着以外の幼少期の影響が混ざってて。しかし、気が向いたときに、もう少し追記しようと思います。