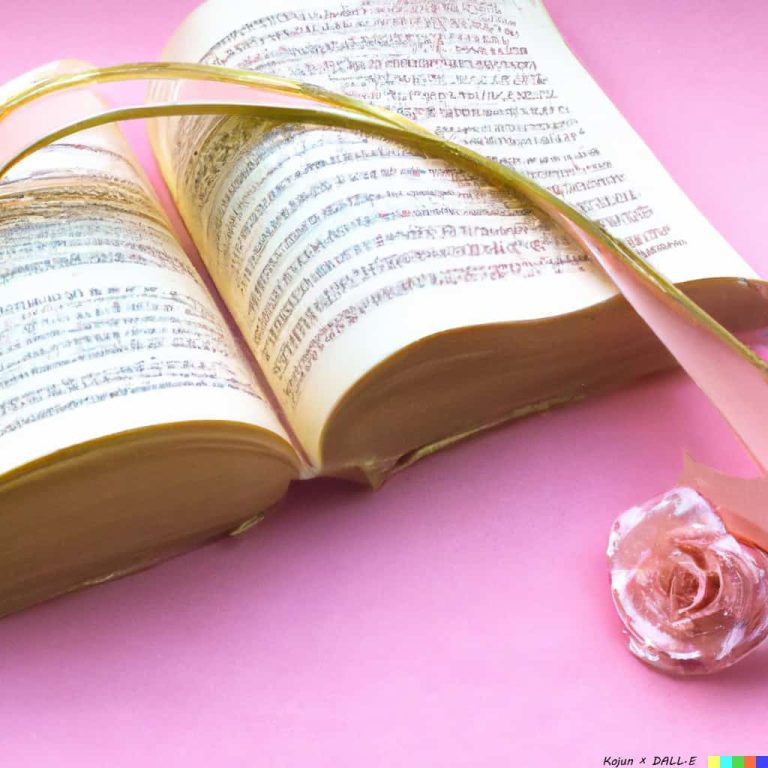克服は意味を消化する
苦しみを克服する過程というのは、単純に治す場合と、その意味を消化する必要がある場合とがあるように思います。
とくに後者の場合に、克服と呼ばれるように思います。
私のクライアントさんたちは治療というよりも克服をする人が多いかもしれません。
苦しさには意味がある。それをひとつひとつ解いてゆく。それがセラピーの始まりなのか、仕上げなのかは様々です。
見つけようとするわけでもない
だからといって、苦しみの意味を見つけようとするのではありません。「さあ苦しみの意味を見つけよう」ではなくて、苦しみ声を聴くと意味がわかる、解けるという感じです。
こうなればよくなるってことと、そうすればよいってことは違うのです。そこが科学技術とは違うところ。
心理プロセスは再現をしようと作為的になると、異なるものになってしまいます。心理プロセスは促されるのではなく、許されるのですね。
克服の道というのは、解けないことを責めずに、解くことを諦めずに。
苦しみの意味は目的でも原因でもない
苦しみに意味がある、それはなにかを教えてくれている、ということ。
プロセスワークではシグナルと呼ぶでしょう。ノックとも呼ばれるようですが、それはちょっと支援者都合な感じがします。
支援者は成果を出したいので、目的論を好みます。それは「苦しみはなにを促しているのか」といった視点ですが、それだと苦しくて進めないこともあります。
その場合、目的は意味ではないんですね。
シグナルを目的論で解釈すると、すり替わってしまうことがあります。たとえば「社会復帰しなきゃ」とか逆に「社会に背を向けなきゃ」とか、それは世間への反応であってシグナルの意味ではなかったりします。
意味がわかることで目的がわかることはありますが、意味不明のほうが深いです。
苦しみの理由を知ることが必要。それのほうが意味に近い。SOSシグナルが聞こえたら、なんのSOSなのか理解する必要がある。
なんですが…、原因論になっちゃうのも、すり替わりなんです。
原因→苦しみ→目的
「Cだから苦しい」「苦しいのはGすべきということだ」はどちらも意味であるとは限りません。ただ、意味がそのような言葉で表現されることはあるでしょう。
原因や目的に惑わされず、苦しみそのものの意味を解いてゆく。
それは本当の気持ちを知ってゆくということだったり、何が起きているかをあるがままに眺めることだったりします。
原因解釈、目的解釈ではなく、かといって身体感覚に留まるだけでもなく、なんで苦しんでいるのか、を知ること。原因ではなくて理由。
それは原因論を選ぶこと、目的論を選ぶこととも関係してると思います。その原因論や目的論で幸せになるのか、苦しみそのものに聴いてみるってことでもあるかもしれません。
でも、苦しみに意味があるというのは、原因や目的のことではないという視点が参考になればと思います。