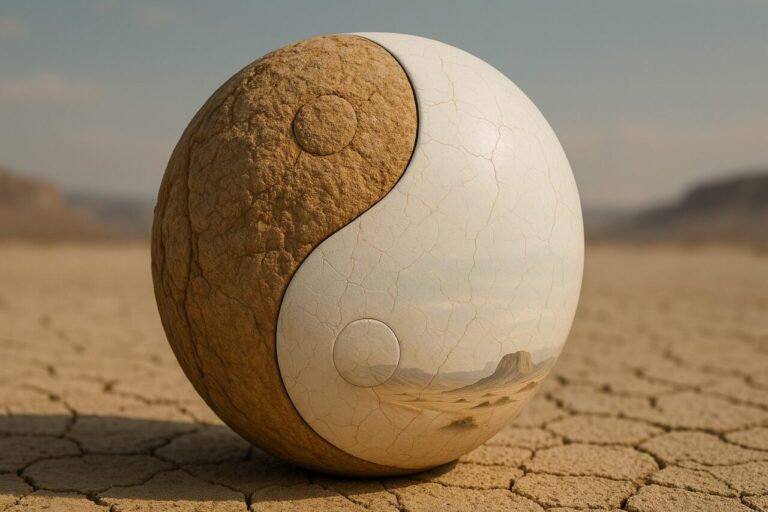ウーンデッド・ヒーラー
「ウーンデッド・ヒーラー(傷ついた癒し手)」はユングの概念です。
心に傷がある(当事者体験のある)人が心理支援に能力を発揮するというような意味です。
※Kojunは同じような意味でネイティブ・セラピストという言葉を使っています。
泳いだことはないけど教え方は知っているという水泳コーチと、泳いだことがある水泳コーチの違いのようなものです。
傷をなめ合うような世界を想像する人もいるようですが、そういうことともだいぶ違います。不幸自慢でもありません。当事者体験がある人にしか見えないことがあるということです。
回避し難い現実を背負う人に必要な、マインドフルな視野、「みじめじゃないぞ」でもなく「みじめだ」でもない何かを一緒に見ることができるからです。
Kojunのクライアントの半数弱くらいが、対人支援に関わっています。心理実践や心理ケア技法を10年以上学んでいる人もよくいます。
歴史に残る臨床家たちにもネイティブ・セラピストはたくさんいます。喪失やウツの体験から着想を得たメラニークライン、境界性パーソナリティ障害の当事者のリネハンなどなど。中井久夫なども当事者ではないかと言われています。ユングは不登校だったそうです。
欧米では心理セラピストになるためにはせめてクライアント経験を積むことが一般的だそうです。
ヘルシー・ヘルパー
また、「強いものが弱いものを助ける」という世界を期待する人は、ウーンデッドヒーラーは頼りないと思うようです。
例えば荷物運びなどで、体が強い人が体が弱い人を助けるというのならそうでしょう。が、それはヒール(癒し)しているのではありません。
だいぶ誤解のあるこの言葉です。「大丈夫な人が、大丈夫ではない人を助ける」というのが常識ですから。
そのように、傷のない人が傷のある人を助ける世界観を、私はヘルシーヘルパー・モデルと呼んでいます。
当事者の力
アダルトチルドレンが他のサバイバーと会って、目があってニッコリしてもらった。それがきっかけで自身の心の問題が一気に回復に向かったという例があります。
セクシャルマイノリティのワークショップでも、不思議な性別超越者たちが集まる場で、なんとも言えない赦しの世界が創られて、それまで苦しみと怒りたけだった人が、ふと穏やかになり、生き方が変わっていったこともあります。
それらは傷ついて生きてきた人が、そこにいる、そのプレゼンスだけで人の心を癒やすことがあるという例です。
ピアサポートから治療者や癒し手へとたどり着くケースが、ウーンデッド・ヒーラー・モデルです。
次の書によると、ケアすることと、ケアされることが表裏一体となり、患者やクライアントの中の内なる治療者が活性化するとも。
パッチ・アダムス。ピエロの格好をしたりして、患者を笑わせる医療を実践した精神科医だ。彼はもともと自殺企画のあるうつ患者だったのだけど、精神科病院に入院しているときにほかの患者を笑わせて元気づけたことが回復のきっかけになる。だから(中略)患者をを笑わせ、癒やす。そして、自分もまた癒やされ続ける。
(中略)ブラックジャックは幼きころに爆弾によって体をバラバラにされた。それをある名医が縫い合わせて助けてくれた。すると成長して医者になったブラックジャックは天才的な外科技術を駆使して、人のことを切り刻み、そして縫い合わせる。
東畑開人『居るのはつらいよ ケアとセラピーの覚書』
ちなみに、パッチア・ダムスは実在の医師の実話がモデルです。
たとえば、性別やセクシャリティで悩む人のカウンセリングに、セクシャルマイノリティのカウンセラーは悪くないでしょう。
今日ではLGBTQを異常だと言う心理支援者はいませんが、それは教科書が改訂されたからにすぎません。多くの心理支援者がLGBTQを異常者だと扱っていたことは、当事者である私は実体験として知っています。再び教科書が改訂されてLGBTQが異常とされれば、多くの心理支援者はまた態度を変えるでしょう。
しかし、「みんなと違う」という実体験に基づいて人を観る力を養った人たちは、最新の教科書がどうあろうとも態度を変えたりはしません。当事者に必要なのは心理支援者はのはそんな人たちでした。私はそんな人たちのおかげで生き延びました。
またたとえば、犬に噛まれた恐怖症のセラピー依頼があったとしますね。当事者体験を重視しないセラピストなら、恐怖症のエビデンス資料や標準マニュアルなんか調べます。それは小説の最後のページだけ読むようなものでしょう。
ネイティブセラピストの私はまず近所のよく吠える犬のところに行って手を出してみました。まず噛まれてみないと恐怖症はわからないってことです。
やってみればわかりますけど、呻る犬の前に手を出すだけでも、けっこう恐いですよ。体験せずに資料を読むなんて、何も知らないと言えます。でもそれが専門知識と呼ばれているものです。
とはいえ、なんらかの当事者体験があるからと言って、他人の気持ちがわかるとは限りません。わからないということがわかるのかもしれません。それでも何かが違います。
さらに言えば、ユングの言うウーンデッド・ヒーラー(傷ついた癒し手)というのは、たんに当事者の気持ちがわかるということよりもっと大事なことを言っているのだと思います。
ウーンデッド・ヒーラーの価値が認められる(というよりは、心に傷なんかないという人が支援者に向いいるという誤解がなくなる)といいなと思います。
*専門的な訓練が非支援者との関係を疎遠にするということについての先人の体験にも通じるところがあるように感じます。心理セラピストの世界でも「初心者のセラピーの方が上手くいく」というのは何度も聞いた意見です。
*知識と体験
セラピスト自身がどれくらい深く潜ったことがあるかが、クライアントをどれくらい深く支援できるかの限界になると昔から言われてきました。
当事者の体験知とは、多くの場合、「正論が通用しない世界をどれくらい身をもって知っているか」だと思います。それは「どれくらい矛盾を呑みこんでいるか」だと思います。
また、クライアント体験も大切です。諸外国でもセラピストのクライアント体験は重視されています。
患者としてのセラピストについて、ポウプとタバシュニクがアメリカ全土を調査したところ、個人療法を受けたことのある84%のうち、有益でなかったという回答はわずか2名でした。
『援助専門家のための倫理問題ワークハンドブック』p.61, 第2章
セラピストもクライアント体験をしたほうがよいということです。であれば、当事者は本格的なクライアント体験が出来ます。
しかし、日本には「カウンセリングを受けることはカウンセラーとして恥だ」と言う心理職もいます。ヘルシー・ヘルパーでなければならないという考えですね。
心理の専門家は「全てを知っている人」「最も知っている人」ではない
ガンを患ったことのない医師でもガンの治療は出来ますが、トラウマ等を克服したことのない人にはトラウマの治療は難しいです。・・・というのはやや言い過ぎですが、その差は大きいです。(トラウマ経験者なら誰でもトラウマ治療ができるというという意味ではありません)
トラウマ支援に当事者性が重要な役割を果たすということに対して「それはガンにかかったことがない医者はガン治療が出来ないと言うようなものだ」と反論する専門家は、ほんとうにトラウマを解っていないのだと思います。むしろ、本当の専門家は「自分たちの専門知識はトラウマの一側面でしかない。当事者は他の次元をも見ている」と言います。医療とちょっと違う心理支援のこの性質は、ガンを治療する(レーザー光焼くなど)のは主に医師ですが、トラウマ克服をするのは本人だからかもしれません。むしろトラウマを自分が治していると勘違いしないのが専門家でしょう。
ここでいうトラウマというのは広義トラウマのことで、PTSDのことではありません。そしてトラウマ以外の心の悩みに多く当てはまると思います。
ですが、最近は特に「心理の専門家」が「最もよく分かっている人であるかのように祭り上げられています。最近のトラウマブームで専門家が知ったように解説していることは、かつて当事者たちが訴えていたが専門家たちが無視していたことです。
大切な人を亡くすこと、それは誰にでも訪れる喪失体験である。しかし、私たちはその体験がどん苦痛を伴うかを、「そのとき」が来るまで実はよく知らない。
『グリーフケア 死別による悲嘆の援助』高橋聡美
ボクは認知症の臨床や研究を半世紀にわたって続けてきました。でも、自分が認知症になって初めてわかったことがいくつもあります。
『ボクはやっと認知症のことがわかった』p.66 長谷川和夫
彼らは、親に虐待される痛みも知らず、子どもの頃に家出や自殺を試みたこともない。(中略)彼ら専門家の知識は、虐待から必死に生き残るために具体的で泥臭い方法を実践で積み上げてきた当事者たちの豊かな知恵には遠く及ばない。
『さよなら、子ども虐待』p.161 細川貂々・今一生
自分自身がそうした体験(息子が脳死状態)をしている時に、脳死関係の専門の学界の先生に会ったり、学会の講演を聴いたりしましたが、そういう場での専門家の発言は非常に冷静で客観的で科学的なわけです。「どうして日本では臓器を提供しないのか」「どうしてそんなに死んだ体にこだわるのか」「脳死を人の死と認めない看護師もいるようだけれども、そのような看護師は看護師じゃない」などと堂々と言うわけです。(後略)
柳田邦男『悲しみとともにどう生きるか』
自分のこととして体験した人と、ただ専門的に学問としてやっている人の違いは大変に大きい。
心理の専門家は「全てを知っている人」「最も知っている人」ではなく、「形式知を知っている人」というのが実際のところとなっています。
体験による暗黙知 vs お勉強による形式知
形式知を知っている人という意味での専門家を、私はスペシャリストであってエキスパートではないと表現しています。
ウーンデッド・ヒーラーが持つ当事者体験は多くの暗黙知を含んでいます。言葉にならない知のことです。一方で、ヘルシー・ヘルパーや講義や試験勉強で作られた心理職は形式知を豊富にもっています。これは主に言語化された知のことです。
形式知を軸に学んでいる人たちは、How to を蓄えようとするようです。「こんなときは、どうすればよいですか?」という質問をして、「○○するとよい。△△しないほうがよい。□□先生もそう言っていた」というのを蓄えていこうとします。たとえば、「共感するときは、『悲しいのでしょうか』ではなく『悲しいのですね』と言ったほうがいい」とかですね。いや、ほんとにそういう話をしています。これはルール・ベース学習と言って、昔の人工知能研究が失敗したアプローチです。どうしても失敗するのです。「実家に帰省してきました」というクライアントに「それはホッとしたでしょう」と言うと、実はクライアントにとっては実家は心休まる場所でなかったなんてこともあります。「そのような場合は、『ホッとしましたか』のほうがよい」というように例外ルールを付け加えてゆくのですが、キリがありません。AIに犬と猫を見分けさせるために「耳が尖っている場合は猫だ」と教えても、耳が尖っているシベリアン・ハスキー犬がいたりして、例外ルールだらけになって破綻しました。
暗黙知(体験知)を軸に学んだ人は、近年の深層学習AIのように、先に言葉にならない(ルール記述できない)暗黙知を蓄えています。そして最後に形式知でまとめをします。How to do ではなくて What to beを蓄え、手法をWhy to doを軸に学びます。これが犬と猫を見分けられるAIと通じるところです。
ある先生は「『プロカウンセラー(たとえば心理師?)』と『素人だが良いカウンセリングをするカウンセラー(心理師以外の相談員、あるホステスさん、初心者ウーンデッド・ヒーラー?)』の違いは、プロカウンセラーは自分のやっていることを言語化できるということだ」と言ったそうです。なるほどです。多くの専門家は「なるほど、そこがプロカウンセラーの優れているところか」と納得しますが、私は「なるほど、そこがホステスさんの優れているところか」と納得します。
「そのホステスさんは暗黙知だけに頼っているが、プロカウンセラーは同等レベルの暗黙知に加えて形式知も持っている」というのであれば、プロカウンセラーの方が優れていると言えるでしょう。しかし、実際には「プロカウンセラーは形式知だけに頼っているが、そのホステスさんは暗黙知だけに頼っている」というのが現状に近いと思います。どっちもどっちかというと、暗黙知だけに頼っているほうがかなりマシというのが私の実感です。どちらにしても相談する側としては全て鵜呑みにしない注意は必要ですが。近年のAIがちょくちょく間違ったことを言ってくるが、そこを気を付けて使えば役に立つというのに似ています。
ムカデのダンスのお伽噺をご存じでしょうか? ダンスが上手いムカデさんに「どのように足を動かしているのですか?」と尋ねたら、ムカデさんは言語化しようと努力して、踊れなくなってしまったというお伽噺です。そのホステスさんがプロカウンセラーの技術を学ぶと、その能力は落ちるかもしれません。私も言語化された「こんなときは、こうするべき」系の専門知識を勉強したことで、セラピストとしての能力は一時的に少し落ちました。ムカデさんや私に起きたことは、おそらく普遍的な原理なのでしょう。
優れた支援能力のあるホステスやバーテンダーやウーンデッド・ヒーラーは、「学識がないから言語化できていない」というよりは、「言語化されない知をもっている」のだと思います。
教科書を読んでやってみて、やってみた体験から学べば、「上手くいくときはこんな感じなのか。上手くいかないときはこんな感じなのか」を覚えます。教科書を読んだだけ(先生に言われたことを信じただけ)では、「こんなときはこうする。こんなことはするべきではない」ということを覚えます。前者はクライアントとインタラクティブに付き合えますが、後者は習ったことを押し付けることしかできません。
心理学では「言語隠蔽効果」というのがあります。言語化することで非言語の記憶が失われるというものです。人の顔を見て覚えるだけよりも、「丸い顔」とか特徴を言葉にして覚えた方が、もともとの顔を思い出せなくなるわけです。心理学の専門知識を先に学んでから実践経験を積むというのが、どれほど心理職としての能力を損ねるのかを説明しているように思います。心理学(の言葉)を知らないで人と接してきたホステスさんや自分と接してきた当事者が、いかに実際に起きていることを高解像度で覚えているかも示唆しています。
つまり、暗黙知とは、「まだ言語化されていない未完成、未分化の知」ではありません。言語化すること(言語化された部分だけを残すこと)は知の劣化です。
言語化される以前の「体験されるそれそのもの」をdirect referentと言います。心理師養成ではこれを育てることを捨てています。捨てていなかったらウーンデッド・ヒーラーを排除せず貴重な仲間とするでしょう。
ウーンデッド・ヒーラーはdirect referentを持っています。それは専門家が嫌い、たいして役に立たないことにしたいものです。
「実家に帰ってもホッとしない人もいる」という例外ルール(専門知識)を知らなくても、なんとなく「ホッとしましたね」と言わないほうがよさそうということが解る(ときがある)、あるいは言ってしまったときに異変に気づきやすいのです。なぜ気づいたのかについて言語化できないからプロカウンセラーよりも劣っているのでしょうか。言語化できない知を持っていて、それを使えているのだから、優れているのではないでしょうか? 私はそのホステスさんに「あなたは無意識にこんなカウンセリング技術を使ったのですよ。これからは、そのことを自覚的にやりましょう」と教えても人を癒す能力が上がるとは思えません。たぶん、的を外すようになるでしょう。
暗黙知に耳を傾けながら、形式知を参考にするということを習得するのは、暗黙知が乏しい人にとっては難しいです。「だって、○○先生もこう言っていますし」となってしまうのを何度もみかけました。それに比べて、クライアントなどの自分と向き合い始めたウーンデッドたちの学習は高速です。彼らは理論なんて信じないので、理論を上手く使いこなします。
優れた暗黙知を使う人たちの「言語化できない」は必ずしも「自分が何をしているのか分かっていない」というわけではありません。自分が何をしているのか分かっていないのは、むしろ形式知でハウツーを学んだ人たち、権威を妄信する専門家たちも多いです。
形式知は暗黙知を整理整頓するに過ぎません。暗黙知なき形式知は危険だと思います。
脳科学においても伝統的には左脳が「優位半球」と呼ばれていましたが、現在ではむしろ右脳が「優位半球」と呼ぶばれるべきなのではないかという意見もでてきています。
ただし、他の専門家に相談したり、他の支援者と連携するためには言語=形式知が必要になります。なので、ネイティブ・セラピストも専門知識の勉強は必要になります。また、自分の暗黙知のカバーしな範囲については知識で補う必要があります。全く勉強しないネイティブ・セラピストも、暗黙知を軽んじる知識ベースな専門家も、あまり頼りになりません。
体験知というのは知識の分野ではありません。体験知が乏しいというのは、「私が○○心理学は専門外なので詳しくないです」というのとは次元が違います。ですので「トラウマの専門家」なんていうのを作ってもウーンデッド・ヒーラーの代わりにはならないんです。ウーンデッド・ヒーラーと補い合う役割の専門家にはなれるかもしれませんが。
また、当事者体験談を読んだり、講演で聞いたりするのも、すでに言語化されているので、どちらかというと形式知です。「体験についての形式知」は体験知ではありません。体験談を聴いたときに自分に起きる反応は体験知ですが、他者の体験談は体験知ではありません。「当事者の方にとっては、こうなんですよ」というのを学ぶことは、当事者への理解力をある程度高めますが、それはウーンデッド・ヒーラーになることとは異なります。
哲学者のカントは似たような考えを「学校知」と「世間知」という言葉で表しており、世間知がないとホンモノの哲学者にはならないと言っているそうです。一方で、臨床心理の分野では「学校知」をもつ専門家をホンモノと呼ぶ伝統がありますが。
これらのことは、「形式知を極めることで暗黙知が生まれる」というアプローチはあまり現実的ではないということを示唆しているように思います。ただし、形式知を極めることで暗黙知への理解が生まれるということあり、スペシャリストはエキスパートと補い合う存在となりえるのだと思います。しかし、高い地位のスペシャリストたちは、暗黙知を理解せず、「形式知(確かなモノ)は暗黙知(あやふやなモノ)よりも優れているのだ」と思っているので、資格制度などを整備することでエキスパートを魔女狩りして撲滅することを目指してキャンペーンを行うことがあります。(後述、ウーンデッド・ヒーラーの受難)
知識に喰われる専門家たち
体験することは知識とは大違いだったという体験談は、心の悩み、心理カウンセリングの場でもよく聞きます。
今日では高度な専門知識を有したカウンセラーを増やそうという動きがあるようです。「専門知識が人を救う」と講師もいいます。
一方で私が受けた心理セラピーのトレーニングでは、知識を思い出そうとしていると「どこ見てるの? クライアント(来談者)を見なさい」とよく言われました。いかに知識に喰われることなく状況を判断できるかが問われるのです。瞬間瞬間にセラピストが何者なのかが問われます。それは自身の傷をどれくらい見つめたかが問われるのです。そもそも傷がない人はトレーニングすらできないわけです。
教科書には心理学者や精神医学者が心理療法を作ったかのように書かれていますが、本当は当事者達の試行錯誤により作られたのだと思います。心理療法は実践から生まれます。誰がやったんですか、ってことです。
今日では、精神的苦悩によって力を奪われた経験をもつ人を「経験専門家」とよぶことがあるほど、個人的な経験が、重要なエビデンスの源となっています。
『精神科診断に代わるアプローチ PTMF』メアリー・ボイル/ルーシー・ジョンストン,p.ⅵ
歴史的にみれば、アメリカにおけるソーシャルワークは一つの目的と動機だけによって実践を開始した。そして、徐々に知識と技術の体系を発達させ、ようやく理論をつくり上げたのである。いかなる場合も、初めに実践があり、その後に専門用語が作られる。
『ケースワークの原則』F.P.バイスティック,p.8
これは、存在 vs 知識 の対立だと思います。対立しなければいいのでしょうが、対立してしまっているように思います。。個人的な意見としては、バランスをとるというよりは、両方を大切にできたらと思います。
試行錯誤したかどうか
いくつかの類似の実験研究によると、予めゲームのルールを教えられた実験群と、試行錯誤によってルールを見つける必要のあった統制群を比較した場合、最初は実験群の方が成績がよいが、やがて統制群はそれに追いつき、その後にルールが変更されたときの適応は統制群の方が早いそうです。経験から学んだ者よりも、「正しい知識」として学んだ者は「私たちは正しい」というルールの呪縛を受けるというわけです。それは精神病理に加担するものとしても研究されています。
*とくに最近では、多様性を否定してオールマイティを目指す「心理師」カリキュラムが詰め込み教育になっているため、試行錯誤なんかしている暇はないと聞いたこともあります。そういう意味では旧き臨床心理さんたちのほうが、サバイバーへの理解は深かった(正解を知っているという意味ではなくて、解っていないことを解ってくれる)ように思います。
ウーディッド ≠ ウーンデッド・ヒーラー
ここで補足ですが、傷ついた人(ウーンデッド)のすべてがウーンデッド・ヒーラーになるわけではありません。
「傷ついたあなたはカウンセラーになれます」というようなカウンセリング講座の宣伝文句は誤解を招きそうです。それが自分の道なのか知るために勉強してみるのはよいと思いますが。
心理支援を職業にするなら、少し勉強する必要もあります。それは、特異とする支援技術とその適用範囲、リスク管理に関すること、心理支援業界の全体像と大まかな自分の位置に関する知識などです。
ただ、ウーンデッド・ヒーラーは職業を表す言葉ではありません。ですから、心理支援を職業としなくても、自然体でウーンデッド・ヒーラーな人もいます。
それを職業やサービスにしたウーンデッド・ヒーラーを私はネイティブ・セラピストと呼んでいます。
ですが、副業の多い業界なので、厳密に区別するのは難しいです。
また、ウーンデッド・ヒーラーがウーンデッドと異なる点として、目標をクライアントと共有しているか、見立て(こうなっている、こうなればよさそう)を持っているかということもあります。
「抵抗」をパスするウーンデッド・ヒーラー
他の節と重複しますが、書いておきます。
精神療法の世界ではクライアント(患者?)の「抵抗」に焦点があてられてきました。クライアントというか人は皆、世界観や自分観の変化を嫌う反応をするということ。どうしたら抵抗を解消できるかが技法だったりします。
しかし、ウーンデッド・ヒーラーは抵抗を誘発しません。たとえば、「あなたはにげているんだと思いますよ。逃げるのをやめるといいと思います」なんて言ったら、普通は抵抗が起きます。しかし、ウーンデッド・ヒーラーやネイティブ・セラピストだと、「やっぱりそうですか。もっと言ってください」となることも多いです。ですので、「抵抗をなんとかする」というのが技法のメインテーマにはならなかったりします。ですので、「抵抗」対策以外のことにエネルギーを注ぐことができます。
抵抗があるのは視点の変化に痛みがあるからです。ですので、変えようとするより支持的がベースになります。これがヘルシー・ヘルパーとの違い。
ですが、ウーンデッド・ヒーラーは見立てや目標を持っています。変えようとはしないけど、どう変わればよいかは一つ以上の仮説を持っています。これがウーンデッドとの違い。
「仮説を持たずに興味を持て」と教える先生もいますが、それは仮説を持つと変えようとしてしまうからです。ですが、ウーンデッド・ヒーラーは「仮説を持っても、変えようとはしない」という態度を実践しやすいです。自分が「分かっているけど、変えられない/変えたくない」という段階を体験してきたからです。抵抗とともにいれば、抵抗は問題ではなく貴重な体験となります。「もっと抵抗しましょうよ」と言うこともあるくらいです。
ウーディッド・ヒーラーの受難
大学で六年間学び、単位をとり、試験を受けてきた専門家たちは、「こんなに頑張って教育を受けたから、自分は人を支援できるのだ」という世界観を持ちます。
それは裏返って、「自分と同じ教育課程を経ていない者が心理支援など出来るはずがない」という思いを生み出します。自分は大変な時間とお金と労力をかけて専門家になったわけですから、大学で心理学を専攻していない者に心理支援が出来てしまったらたまったものじゃありません。
それはかつて医師が臨床心理士を嫌っていたのとよく似ています。
院卒の心理師は「大学も出てない人がカウンセリングするなんて信じられない」と言ったり、様々な方法で自分と異なるバックグラウンドの者を心理業界から追い出そうとします。というか、そんなつもりはなすとも認知的不協和が生じて、追い出すべき邪悪な者に見えてしまうのです。ウーディッド・ヒーラーは学歴がないことも多く、この憎しみのターゲットになります。
これは、情報科学の修士号をもつ者が高卒のエンジニアを否定しない、それどころか彼らを助ける技術を開発することと大きく異なります。
また、大学教員にとっては「大学で学んだ人しか心理専門家になれない」という方が都合がよいですから、大学教員が法制度に関わればそのように作るというバイアスが働くでしょう。国家資格の社会人ルートを廃止させました。
ですが、大学で六年間学んでも、十年、二十年の試行錯誤を続けてきた当事者の体験世界を超えることはできないと思います。実際に私がカウンセリングを受けて役に立った何人かは学歴のないウーディッド・ヒーラーでした。それは「当事者体験があるから人の痛みがわかる」という程度のものではありません。1 ウーンデッド・ヒーラーは寄り添うもなにも、最初からそこにいます。2
大学で学んだとしても、当事者本人の知恵や力をみくびり自分の支援のおかげだと勘違いしていなければ、ウーディッド・ヒーラーの価値を無視することはないでしょう。
「あなたたちの典型的な思考だ。自分たちは理性的で優っていて、他者は未開で劣っている。」移動民族の少女ドゥラカ
『チ。 ―地球の運動について―』S1 E17 魚豊・原作
・・・と、この作品はフィクションですが、人類の常を言い当てているように思います。
私はどちらの気持も少しずつわかります。
また、高学歴者が低学歴者を叩く背景には、心理職は高学歴であっても非常勤・アルバイトであることが多く、その収入の低さに追い詰められている背景もあります。コミュニティが追い詰められると、一部の者たちに「彼らのせいだ」と責めるスケープゴート化現象が起こります。これは世界中の被災地などで起こる現象でもあるそうです。性的マイノリティーの世界でも、ゲイがバイセクシャルを批判・攻撃するなどの形で生じていました。
たとえば、ある自称カウンセラー(無資格者)が不適切な本を執筆したということで、それをある教授は「自称カウンセラー問題」(無資格のカウンセラーはけしからん)と呼びました。しかし、無資格者のうち不適切な本を書いたことがある人は1%にも満たないでしょう。不適切な本を書いた無資格者が1人いたことを取り上げて、それを全ての無資格者が不適切な活動をしている明らかな証拠であるかのようにネガティヴキャンペーンを行うというのはスケープゴーストの典型でしょう。それを言うなら、大学院を卒業した心理士が間違いや失敗をした例を私はいくつか知っています。しかし、それをその教授は「臨床心理士問題」(臨床心理士はけしからん)とは言わないでしょう。そして、この文章を読んだら怒り狂うでしょう。
被災地やマイノリティーコミュニティで起きてきたこの現象は、臨床心理業界においても、とても強い力で人の心を動かしています。
ウーンデッド・ヒーラーは権威・学歴を持たないことも多く、高学歴者の「人を助けることができる特別な存在でありたい。特別ではない君たちはカウンセラーを名乗るな」という認知的不協和、「高学歴なのに定収入なのはおかしい。あいつらのせいだ」という気持ちから生じるスケープゴースト化のターゲットとなりやすいようです。
そして、かつてはウーディッド・ヒーラーと助け合う臨床心理士(大学院卒)たちがいました。その思い出を大切にしたいと思います。
当事者性を持つ支援者が気をつけるように言われていること
ウーンデッドな支援者が気をつけることとして、よく挙げられるのは次のようなことです。
「巻き込まれる/貰っちゃう」説
クライアントの話を聴いてフラッシュバックが起きるとか、落ち込むみたいなことが言われます。うーん、学び初めの頃に学習中に起きるかもしれませんが、あまり目撃したことはありません。いろんな対人支援職の方にアシスタントをお願いした経験からすると、ウーンデッドではない人の方が支援場面でパニックを起こしやすい印象はあります。
とくに広義トラウマ(愛着や複雑性トラウマを含む)の領域では、克服の旅をしてきたウーンデッド・ヒーラーはお互いに巻き込まれそうになるトラブル経験は豊富で、それを生き抜いてきたわけですから、むしろある意味で専門性は高いです。
ただ、教科書的なリスクや倫理のことも学んでおいたり、相談先を持っておくことは必要かと思います。
「メサコンになる」説
メサコンとはメサイヤ・コンプレックス(人を助けることで自己肯定感を得ようとする極端な性質)のことです。メサコンもその病んでいる印象から、背景に傷つき(おそらく自己肯定感などに関する)があることが示唆されますが、だからといって逆にウーンデッドは全てメサコンになるというのは誤解です。
むしろ、そのような偏見を持った人が傷ついた人の心理支援にあたっていることのほうが恐ろしいように感じます。
ちなみに、心理支援者の中には自分がメサコンなのではないかと心配する人がいますご、本格的なメサコンは単に「人を助けたい」とか「支援に遣り甲斐を感じる」というレベルではなくて、必死で不幸な人を必要とする、不幸な人が見つかると嬉しそうな顔をするというレベルです。判断基準としては、支援対象者が幸せになると不機嫌になるというあたりでしょうか。そのような本格的なメサコンしんも何人か目撃したことはあります。ただ、クライアント側からはあまり人気はないので、開業領域で活動を続けることは多くないようです。
支援団体の幹部になったり、ヒエラルキーの高い地位についてしまうと、メサコン体質のまま活動することがあるようです。先に述べた認知的不協和や「資格者=(クライアントではなく権威者から)選ばれし者」みたいに思っているというのも、ちょっぴりメサコンに似ています。ただ、それらの場合、本人は「助ける側」の自分が好きなようで、ウーンデッドらしさを出すことはあまりないです。ウーンデッドらしくないところが、それこそ病んでいるような印象かもしれません。
いずれにしても、これらはウーンデッド・ヒーラーやウーンデッドを代表しているわけではありません。
ウーンデッド特有のリスクも、傷つき体験が少ない支援者のリスクも、どちらも多少はあります。なので、それらの両者が心理支援業界の中で共存して補い合う必要があるかと思います。
未来のウーンデッドヒーラー
脳科学や神経心理学が発達すると、職種としての心理師はなくなってゆくかもしれません。むしろ心の支援をするにはAIエンジニアになったほうが活躍できそうです。人混み恐怖症を治療するのに、心理師よりバーチャルリアリティのほうが役立つでしょう。心理師はバーチャルリアリティを開発できませんが、エンジニアはできます。というか既にそのようなVRアプリがあります。彼らが当事者の声を取り入れながらアプリを更新してゆけば、使えるものが出来ちゃうでしょう。心理師たちはこれまでのように権威を使って彼らを潰すことが出来るでしょうか?
ラジオ音声より
制度が整備されると、ウーンデッド・ヒーラーが追い出される。それにより心理セラピー業界から体験知が失われている。
自己一致とは鎧を脱ぐこと。鎧を脱いで癒しを得たことがある人がウーンデッド・ヒーラー。
参考
- 『ケアのたましい』アーサー・クラインマン
- 『シリーズ人間科学6 越える・超える』第2章トラウマ・逆境体験を超える治療共同体 野坂祐子
- 『心理療法家の人類学』ジェイムス・デイビス
- 『当事者と専門家 – 心理臨床学を更新する』山崎孝明
- 『多様性の科学 画一的で凋落する組織、複数の視点で問題を解決する組織』マシュー・サイド(Audibleあり)
- 『精神科診断に代わるアプローチ PTMF』メアリー・ボイル/ルーシー・ジョンストン
- 『ケースワークの原則』F.P.バイスティック
- 『コミュニティ臨床への招待』下川昭夫
- 映画『パッチ・アダムス』(実在の医師がモデル)
- 映画『ディア・ドクター』笑福亭鶴瓶 初主演
- 『居るのはつらいよ ケアとセラピーの覚書』東畑開人
- コミック『ブラックジャックによろしく』佐藤秀峰
- TVアニメ『チ。 ―地球の運動について―』魚豊・原作