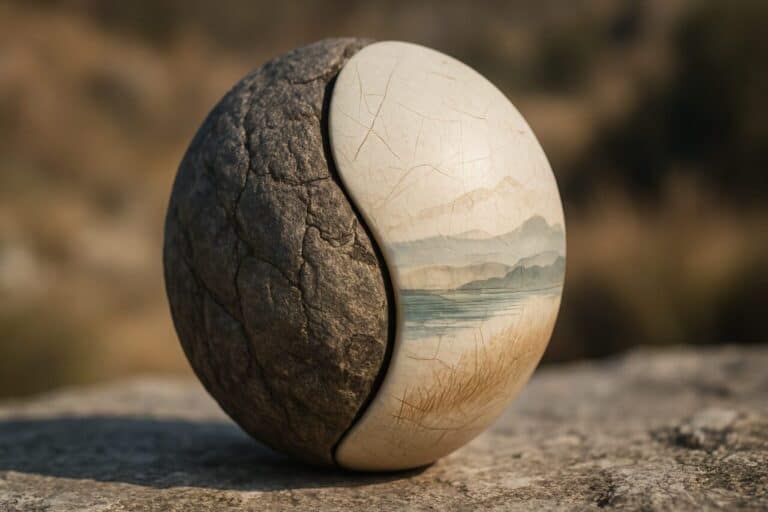専門知識と「知っている」ではない
症状について熟知していても、当事者を診たことあるとしても、それはPTSD等のショックトラウマを知っていることにはならないと思います。
ある女子中学生が同級生たちに継続的に性暴力を受け続けて自死に至った事件がありました。
自殺に先立って精神科医からPTSDの診断を受けていたそうです。ということは、なんらかの事件に巻き込まれていると医師は知ったということです。つまり、その医師は診断はしたけど、助けはしなかったわけです。
助けるというのは、治療のことではなくて、安全の確保をするということです。どんな事件が起きているかわからなくても、診察室から出す前に、加害者から隙間なく守られる環境を整備するということです。
突っ込んで関わろうとすると侵襲性があるかもしれないとか、本人が拒んだり隠したりもするので状況がよくわからないなど、難しいのはわかります。私もどうしてよいか分からなかったことで反省することあります。
ここで言いたいのは、診断できるということと、PTSDになるほどのショックトラウマが何なのかを知っていることは違うということです。「壮絶な体験をした」という事例知識ではなくて、そこからどんな世界が見えてるか、その人が生きてる世界はどのようなものかということです。
上記の助ける=安全確保は、それはそうするべきだというファースト・エイドの専門知識がなくても、それほどのショックトラウマがどういうものかを知っていればそうなるはずです。
ちなみに、私は症状をいくつか経験したことがあります。それは症状を本で読んで学ぶのとは全く違います。それでも、十分には知っていないとも思います。
また、この場合には重大な危害が生じているということが推察されます。
そうはいっても他の患者もいるし、現実的にはそこまで一人の患者を助けることを優先できないとの意見もあるでしょう。それはそうかもしれませんが、だからそれがなんなのかを分かっているということにはならないと思います。
ショックトラウマを「知っている」とはどういうことか
もしその少女が生き残ってその人なりの回復を果たし、そして将来に医師になったとします。そこへ、同じような事情不明のPTSDと診断できるほどの状態の少女が受診したとしたら。おそらく、助けるでしょう。病院を臨時休業にしてでも助けるでしょう。
私のいう「PTSDが何なのか知っている」とは、そういうことです。
そういう意味では、精神科医に限らず、当事者の心理をほんとうに「知っている」心理専門家というのはあまり多くないと思います。私もそういう意味では知ってはいない思います。ただ、「誰も知ってはくれない」というのがどのようなものかは少し知っています。
専門家は当事者ではないので当たり前と言われるかもしれませんが、当事者のそれを知らずして当事者のそれを扱うということがどれほど当事者から遠いものであるかは知る必要があると思います。
「見たことがある」は「知っている」ではない
私も心理セラピーのトレーニングの場で、PTSDのフラッシュバック反応や、それが癒されるプロセスを見学していました、私のクライアントも見ました。ですが、それでもPTSDがなんなのか分かっていませんでした。
自分に起きたことを思い出し、また改めて当事者として事件を経験して、はじめて自分がPTSDを知らなかったことに気づきました。
つまり、なにが必要であるか、当事者の視点で見ていなかったことに気づいたのです。
それまではある意味で事務的にクライアント達を見捨ててきたことに気づきました。それは手法トレーニングプログラムによって補われるものではないと思います。
ニュースなどでPTSDという言葉がお気軽に使われていますが、その言葉を使う殆どの人は何もしらずにその言葉を使っていると思います。