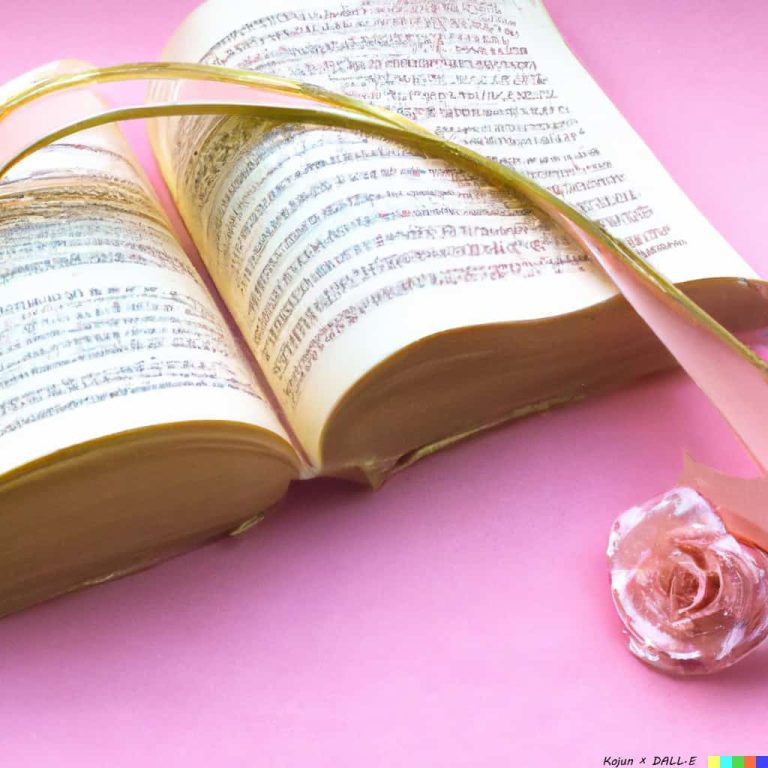Kojunがクライアントやサバイバーにお薦めする書籍などです。
セルフケア
『自律神経にやさしい音楽』(音楽)
by 広橋真紀子
サンプルを聴けばわかります。苦しみの底からよちよち歩き始めるときによいです。瞑想ガイドがなくても、自分と音楽に耳を傾けていれば、ちょっぴり存在できます。
「Progressive Muscle Relaxation Training」(動画)
by Mark Connelly
「漸進的筋弛緩法(ぜんしんて きしかんほう)」という、身体の緊張をゆるめるリラクゼーションのガイドです。自分がいつも力の入っているところを見つけて、そこだけ実践するだけでもよいです。
英語が苦手でも、動画アニメーションが分かり易いので、次を聴き取れれば使えると思います。
「ブリーズ・イン」=息を吸う
「ブリーズ・アウト」=息を吐く
「タイト」=筋肉に力をいれる
「ホールド」=力を入れたまま維持
「リリース」=力を抜く
『「ポリヴェーガル理論」がやさしくわかる本』
by 吉里恒昭
自分の神経系を調整するにあたり、まずはその状態に気づくための本。自律神経の種類を3つの色に喩えて、分かり易く説明しています。
『「安心のタネ」の育て方』
by 浅井咲子
ポリヴェーガル理論の神経エクセサイズです。たくさん載っているので、お気に入りを見つけましょう。
サバイバーは理論よりも、やってみて自分のスキルに取り込むのがよいです。
『増補新版 自分を知りたいあなたへ はじめてのアートセラピー』
by 吉田
エリチャプターごとに心を使って絵を描く方法が書かれています。
『ティク・ナット・ハンの幸せの瞑想』
by ティク・ナット・ハン
ピュア・マインドフルネスの実践を説く本です。プラムヴィレッジ系の実践をするときに教科書のようになります。やさしく書かれていますが意外と深いので、時間をかけて読むことになります。
アダルトチルドレン/ACEs
『複雑性トラウマ・愛着・解離がわかる本』
by アナベル・ゴンザレス
専門書っぽくみえますが、一般向けに分かり易い本です。マニアックすぎず、浅すぎず、ほどよいかと思います。
『子どもを生きればおとなになれる』
by クラウディア・ブラック
Kojunセラピーの原点とも言えます。かつて読み終えたものとして整理しましたが、クライアントと共にあるために、また買い直しました。
『バレット博士の脳科学教室71/2章』
by リサ・フェルドマン・バレット
脳は考えるためではなく、生き残るために進化してきたという観点から、他者との関係が神経系に与える影響を説明しています。サバイバーにとっては、自分を脳科学的にとらえるための読み物になります。
『全訳 念処経 – ブッダの瞑想法』
by 宮元啓一
念処経はマインドフルネスの源泉となる瞑想実践法です。たった60頁のシンプルなものです。
トラウマ・サバイバーは「身体」の部門だけでも、心掛けておくとよいかと思います。
ショック・トラウマ
『赤ずきんとオオカミのトラウマ・ケア』
by 白川美也子
基本的なことが書かれています。
『心を癒すノート – トラウマの認知処理療法自習帳』
by 伊藤征哉・樫村正美・堀越勝
書き込みができるワークブック形式の本です。自分の苦しみの本質が何なのか眺めてみるときに役立つと思います。
「5つの価値」というタグ付けをしますが、分類した結果をどうこうするというよりは、分類作業がその意味に触れる機会を与えるということかと思います。ですので、正解にこだわらずやってみるとよいかと思います。
『心的外傷と回復』
by ジュディス・ハーマン
トラウマに関する古典的名著です。ちょっと専門書っぽいですが、当事者も読んでいるようです。トラウマ当事者が異常者扱いされていたきた歴史から、やっと理解へと向かう専門家の視点です。
『コレモ基礎セミナー』(動画講座)
by コレモ・ジャパン
トラウマや日常的ストレス反応の扱いを神経系の観点から説明しています。自分の状態に気づくこと、スキルを使うことを学びます。
人間関係/問題解決
『NVC 人と人の関係にいのちを吹き込む法 新版』
by M.B.ローゼンバーグ
「非暴力コミュニケーション」という実践フレームワークです。Kojunの言う「感情の所有」を重視しています。
サバイバーのお悩みというよりも一般向けのものですが、家族との感情がもつれている場合に必要になるかもしれません。
昔これが流行ったときには「暴力的コミュニケーション反対!」みたいな暴力的コミュニケーションになってしまった人をよく見かけましたが、それから何年も経って、また見直されてきているようで、健全に分かり易くまとまっているのが本書です。
『自分も相手も尊重し、心理的安全性を高める アサーティブ・コミュニケーション』森田汐生 監修
by 森田汐生 監修
これもKojunの言う「感情の所有」を重視していて、その点ではNVCに似ていますが、NVCは暴力から共感と理解を目指すことを出発点としていますが、アサーションは社会的弱者のエンパワーメントを出発点としています。NVCが暴力的になってしまいがちな人(たとえば相手が部下)向けだとすれば、アサーションは主張することが困難な人(例えば相手が上司)向けかと思います。
『認知バイアス大全』
by 河合伸幸
認知バイアスの本の中でも、おもしろ雑学ではなく、生き方の参考になるように書かれています。
トラウマ・サバイバーの場合は、認知バイアスが弱すぎて身を守れないなんてこともあります。被害者非難、公正世界神話なども興味深いです。
また、トラウマは災害と犯罪のみに起きるのではなく、人類社会に人間関係や集団心理の中に存在するものであり、その根源としてもいずれ学ぶ必要があります。
科学的な視点で捉えたいなら、こちらもおすすめ。
『不登校・ひきこもり・発達障害・LGBTQ+ 生きづらさの生き方ガイド』
by 大橋史信・岡本二美代
インタビューや相談先。福祉事典のようなもの、役所の相談窓口にも情報はありすが、この本は当事者目線で書かれていて、最初に読みやすいかもしれません。
『元法制局キャリアが教える法律を読む技術・学ぶ技術』
by 吉田利宏
必要に応じて法令を参照するための基礎知識を柔らかい表現で教えてくれます。けっこう分厚いので、法学を目指すのでない限りは前半は深読みしないで斜め読みして、次に後半の興味のあるところから読み始めるのがよいかと思います。離婚、相続、消費者トラブルなどに関心があれば民法のあたり、犯罪被害や暴力被害に関心あれば刑法、人権や幸福追求権であれば憲法のあたりです。なお、法令の条文はe-Govというサイトで簡単に参照できます。法テラスにはよくある具体的な相談例が掲載されています。
迷い/自己実現
『トランジション – 人生の転機を活かすために』
by ウィリアム・ブリッジズ
Kojunが心理セラピーで開業した当初にコンセプトにしていた概念です。何かが終わり、ニュートラルゾーンを経て、何かが始まるとう概念です。新しい始まりが上手くいかないとき、旧い自分がちゃんと終わっていないからだというような例が書かれています。
つまり、過去にまつわるテーマから目を逸らすことが、未来を掴めない原因となっているということです。「早く忘れなよ」では済まない場合があるということ。
アダルトチルドレン、小児期逆境体験などのある方にに過去に触れる心理セラピーを提供しているのも、同じような構図が人を生涯にわたって苦しめるからです。過去に触れないという意味での未来志向が上手くいかないとき、その問題をKojunは「置き去りにされしもの」とか「人生の宿題」と呼んでいます。
このような心理セラピーに向かうときも、あるいはそこを抜けて新しい人生を歩み始める時も、この本は参考になると思います。
また、そもそもの相談テーマが「〇〇をやめた、手放したい」であることもあります。その場合は過去に触れる勇気というよりは、ニュートラルゾーンに陥る勇気が必要になるのでしょう。
「終わりから始まる」という構図は「英雄の旅」理論にも似ていますね。ただ、そちらは難しい学者言葉で語られているので、ざっと概要を調べるくらいがいいかもしれません。
『マインドフル・フォーカシング – 身体は答えを知っている』
by デヴィッド・I・ローム
フォーカシングに関する本の中で、実践方法の説明が最も分かり易いとおもいます。自分との対話のスキルです。
『その幸運は偶然ではないんです!』
by J.D.クランボルツ
どちらかというと心理セラピーに成功して、心が自由になった頃に読む本ですが。「計画された偶発性理論」の具体例が書かれています。キャリアの悩みの参考になります。
『窓ぎわのトットちゃん』
by 黒柳徹子
人生の息抜きに。あなたが取り戻したい何かかもせれません。
朗読もあります。
『バンクシー 抗うものたちのアート革命』(ドキュメンタリー)
by エリオ・エスパーニャ
これもまた存在を消される者たちの話かと思います。Points of Youの初期のカードにも彼の作風らしいものが写っています。アンダーグラウンドとアートが融合しているのはセクシャルマイノリティの表現世界にも通じるものがあります。Kojunも福祉などに関わろうとしたときに女装が「汚らわしい」とか、トラウマ経験者は危うい(なにが?)ということで断られたことがあります。
家族と老い
『事例で学ぶ認知症の人の家族支援』
by 福島喜代子・結城千晶
当事者家族の心の進展を4ステップで説明して、心構えなどを提案しています。
福祉ビデオシリーズ『優しい認知症ケア ユマニチュード』(動画・DVD)
by NHK厚生文化事業団、イヴ・ジネスト・本田 美和子監修
認知症の人と接するための技術であるユマニチュードは基本作法として知っておいてよいでしょう。
『ボクはやっと認知症のことがわかった 自らも認知症になった専門医が、日本人に伝えたい遺言』
by 長谷川和夫・猪熊律子(Audibleあり)
長谷川式認知症スケール(HDS-R)の開発者として有名な長谷川医師が、自ら認知症になって書いた本です。認知症の理解というと、その分類とか中核症状/周辺症状とかいう知識的なお話が多いのですが、このような物語的な情報に触れて理解することも、自分の心の在り方を探すうえで役立つかと思います。
その他
『「腸と脳」の科学 脳と体を整える、腸の知られざるはたらき』
by 坪井貴司(Audibleあり)
第2の脳と言われる腸の神経回路、身体機能の一部となっている腸内細菌叢などの影響について解説されています。