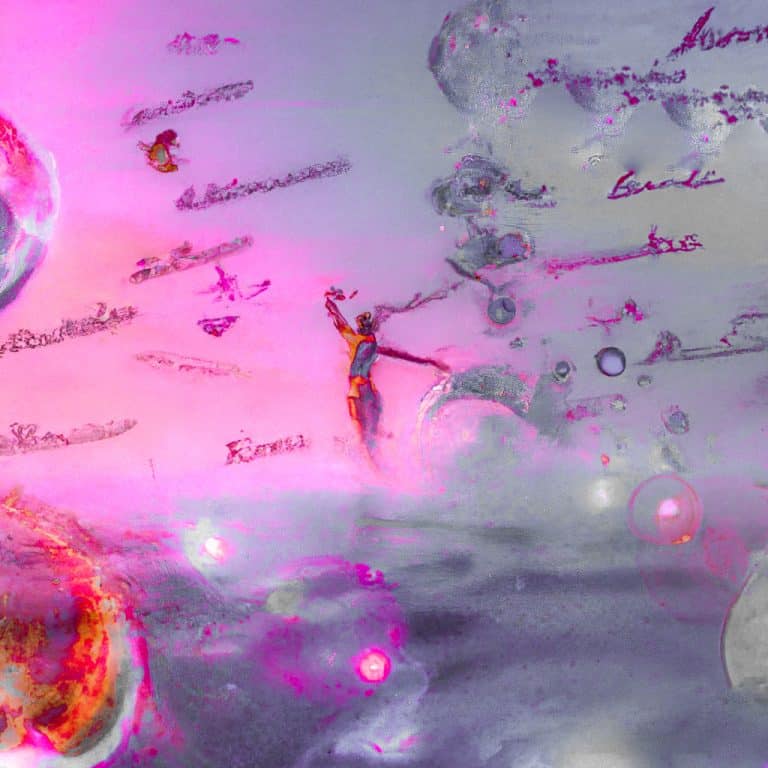Kojunは「認知の修正」という言葉が好きではありませんが、認知療法の元祖(の一人)であるA.エリスの論理療法はちょっと好きだったりします。
※論理療法の発展形である論理情動療法は人間性心理学であるという解説もあるようです。
それもまたクライアントの信念を変更するのですが、A.エリスの論理療法では変更先のことを「新しい効果的な哲学」というように表現するらしいんですね。
「正しい認知」とか「適応的な信念」とかでなく「哲学」っていうところが、本人が選ぶっていう感じがしますし、創造的な感じすらします。
Kojunは「正す」「矯正する」アプローチを好まないのです。
A.エリスさんも「あなたの認知の間違いを指摘したいのではない」と言っています。
「すべきだ」「ひどい」「全てこうだ」などの非理性的ビリーフを手放すことを勧めているわりには、エリスさんの著作が勢い余ってか「非理性的ビリーフを手放すべきだ」「他のアプローチは全くひどい」という論調になっているところがあるのは、クスッと笑ってしまいますが。
具体例:上司とすぐ喧嘩してしまうという感情パターンを解消したい
Cさんはよく上司と喧嘩してしまいます。職場や上司が変わっても繰り返されるパターンなので、どうやら自分の心の問題だなと自分でも気づいています。そこで心理セラピーを受けに来ました。
どうやら上司から注意などされたときに「馬鹿にされている感じがする」らしいです。
浅層っぽい認知療法 vs 深層っぽい論理療法
一般的な認知療法では「上司は私を馬鹿にしている」という信念を、「注意しているだけで馬鹿にしているわけではない(かもしれない)」というようにバランスのとれた信念へと変更してゆきます。そのためにソクラテス対話のような質問を投げかけたり、自身で考えてもらったりするわけです。
論理療法もまた論駁によって信念を覆すように勧めます。「馬鹿にしている根拠はあるのか?」
ただ面白いのは信念の特定のセンスで、「上司は私を馬鹿にすべきではない」などを扱います。そして、論駁によって「馬鹿にされると私はほんとに嫌だが、上司は私を馬鹿に出来てしまう。すべきでないと考えてもなにも変わらない。だが、あまり気にしないことは可能だ」などの哲学を手に入れたりします。
この新しい人生哲学と呼ばれるものは、Kojunセラピーのクライアントが辿り着くものと同じです。方法は論駁ではありませんが。
Kojunのセラピー(再決断療法っぽいワーク)
Kojunのところへ来るクライアントは「ほんとは上司が馬鹿にしているわけではなんだろうなっていうのは分かっているですよ」と言います。なので一般的な認知療法(ベックの認知再構成法など)は試し済みなわけです。それでも、感情反応が変わらない。
で、幼少期に父親から「おまえは馬鹿だからなあ」と叱られていたことを扱ったりします。
※繰り返されているのでなくて、今の上司だけに対して起きている問題であれば、父親でなくてその上司のイメージを使うこともあります。
当時の父親のイメージを目の前の椅子に投影して、少しのやりとりをします。それから父親がいるとイメージした椅子に自身が移動して、すなわち自分が父親の役になって心理セラピストからインタビューを受けます。
「C君のお父さん、どうしてC君に馬鹿だなんて言うんですか?」
そして、お父さんが何かに追い詰められているという感じを味わいます。そして「私(父親)が学歴で苦労したから、その苦しみをCにぶつけてしまっている」と(Cさん演じる父親に)白状してもらいます。
(この内容が現実の父親の心情として当たっているかは、ゆくゆくはあまり重要ではないかもしれません)
そのようなイメージワークをした後で、Cさんに感想を聞くと、次のように世界観が変化していることがわかります。
「前向きに頑張ろうとしているのに、父が馬鹿だ馬鹿だというせいで、前向きな気持ちがいつも台無しになる」
↓
「父さんもがいているなあ。でもさあ、申し訳ないけど、俺には関係ないことなんだよね」
というように。
これもの再体制化ではありますね。
論理療法との比較
幼少期の父親まで遡るかどうかはさておき、論理療法での認知の再体制化は「論駁」という方法が用いられます。基本的には言葉による指摘みたいなものですね。
Kojunセラピーや再決断療法では、代わりにイメージワークを使います。指摘や説得ではなく、気持ちが変わるような新たな視点を体験してもらいます。
また、論理療法理性では理性や正しさを原動力としますが、Kojunセラピーではクライアントの変わりたいという気持ち(あるいは変わることができない苦しみ)を原動力にします。
ただ、A.エリスはユーモアや人間愛をもって論駁するそうです。
Kojunもユーモアは使います。Kojunのよく言われる印象は「面白い」「あたたかい」ですから、ちょっと似ているかも。
治すという感じではなく、楽しいほうを選びませんか?っていう感じも似ていますね。
Kojunのセラピー(リフレーミングっぽいワーク)
クライアント自身で新しい世界を見つけてもらう、もしくはクライアントの中にある真の世界を引き出すというワークの他に、心理セラピスト側から世界を提案してしまう方法もあります。それはリフレーミングと呼ばれます。1
A.エリスもガンガン論駁しちゃうそうなので、リフレーミングに近いかもしれません。
心理セラピスト側から論駁やリフレーミングをする場合には、心理セラピストの生き様が現れます。論理療法もそうなんだそうです。
たとえば、「俺ってダメ人間なんですよ」という信念でスタックしているクライアントに対して、「ダメ人間じゃないよ」系の論駁をかける心理セラピストは多いですが、Kojunは「ダメ人間カンパーイ」とリフレーミングします。
ダメ人間かどうかではなくて、ダメ人間だとダメなのかということについて哲学を提案するわけです。その方が楽しいかもしれないから。いや、そちらの方が本質ですから。
この例なんかは、「立派な資格を持っていないカウンセラーはダメだ」とか言っているカウンセラーが真似してもイマイチですよね。すなわち、生き様が表れるわけです。
多くの認知療法の講座では、クライアントを社会に適応させるような認知修正を例示します。「世界は自分中心では動かない」「誰でも足を踏まれることはある」などですね。
Kojunは、そのような認知修正を促すことはあまりありません。Kojunのクライアントは、たいてい、そんなことはとっくに分かっているからです。
それはKojunがこれまで散々に「どうせお前のワガママだろ」「相手の気持ちになって考えろ」「素直になれ」などと言われて苦しんできたからです。ですから、クライアントの劣った認知を正そうとは考えません。クライアントがそのような(自分を苦しめる)認知を持ってしまう正当な理由を認めたうえで、リフレーミングを考えるのです。
たとえば、「今朝すれ違った人がぶつかりそうになった。ムカつく」というクライアントに対して、「相手に悪気はない」とか「ぶつかりそうになることくらいあるさ」とかの論駁は提案しません。そんなことくらい分かっているから心理セラピーに申し込んできているのです。
「あいつは私を嫌っている」という自動思考があったとしても、「見知らぬ他人がそこまで私を嫌っているとは考えにくい」なんていう論駁はしません。
ぶつかりそうになったくらいでムカつくのには、よほどの事情があるのだろうと察します。多くの人はそうならないですから。おかしな反応や自動思考であるほど、それはむやみに論駁してはいけないと思っています。
でも、心理セラピーでは、最終的にはクライアントの中の何かが変わります。何を変えるかは、本人の望みに基づいて探してゆきます。社会適応や常識適応に基づいてではありません。