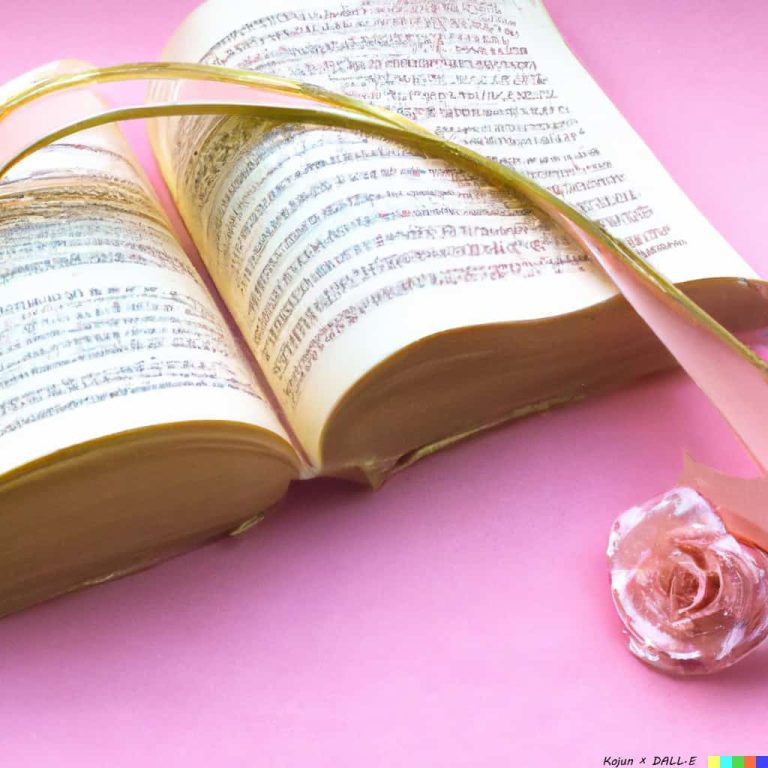統計的エビデンスがある心理セラピーについて
心理セラピー(心理療法)の効果エビデンスというのは、一般的には効果の有無や大きさを調べた統計によるものです。それは母集団(主に平均値)について語るものです。(バラツキが考慮されてないわけでもないですが、それでも母集団と個は別のものです)
統計的エビデンスは、機序(効果のメカニズムの仮説やモデル)が科学的に解明されたという話とは別になりますし、自分にとって必ず効果があるということを示すものではありません。
ただ、誰にも効果がないようなものはエビデンスは出にくいですし、「自分に当てはまるかはともかく、何らかの機序が成立しているらしい」と判断できるかと思います。(ただし、ちゃんとしたエビデンス1)
※おおざっぱなイメージでは、エビデンスがあるといわれている療法で、前提条件が当てはまる人の7~8割くらいに効果があるといったところでしょうか。
次のような場合にはエビデンスが助けになると思います。
- 成果が客観的(症状改善が目的である等)
- すぐに成果を実感できないような実践
- 成果の実感までにコスト(費用や心理的負担)がかかる実践
たとえば、繰り返し何度も継続して実践しないと効果が出ない手法で、何度も途中で止めたくなるようなものです。
心理的負担は簡単に言えば「やりたくない」ってことです。
自分にとってハードルが高い実践ってことですね。それらは、統計的エビデンスを信じて一定期間は継続してみるということになります。
専門家は「エビデンスがあるからやりましょう」と言うかもしれませんが、当事者の視点に翻訳するなら「ハードルを乗り越えるためにエビデンスを支えの一つにする」となるかと思います。
たとえ実感がなくても一定期間は継続するという意味においては、機序の理解も併せて必要になります。統計的エビデンスだけでは、自分が何に挑戦しているのか分からなくなるからです。施術などの受動的に受ける支援と違って、たいていの心理セラピーは主体性が要求されるからです。ですので、エビデンスと機序はセットになるのが理想かと思います。
ですが、自分にとって効果があるかどうかは、どこかの時点で判断して、統計的エビデンスから自分エビデンスへと移行する必要があります。
統計的エビデンスと自分エビデンスの差は、研究者にとっては誤差ですが、当事者にとってはリアリティです。
その移行を試みるためには、どれくらいの期間(または回数)で効果が出るものなのかということを知っておく必要があるかと思います。
統計的エビデンスが不十分な心理セラピーについて
信頼する人の経験則、自分の直感によって自分に必要な心理セラピーや実践を見つけることもあります。
当事者の人生は一度きり
セラピストなどの支援者は、たとえ成果の出ないクライアントがいても、他で成果が出れば手応えを感じることが出来ます。
統計的エビデンスのある手法を選び、そればかりやっていればある程度の成績をおさめることが出来ます。極論を言えば、手法に合わないクライアントは誤差としてしまうことが出来ます。
一方で、当事者にとっては、自分が唯一のクライアントです。
一度きりの人生において、なかなか解決しない悩みであれば、「エビデンスが未だないけど、自分に効果のあるアプローチ」とか「多くの人には効果はないけど、自分に効果のあるアプローチ」を見逃すことはリスクです。支援者はこのリスクを背負っていないことに注意してください。
統計的エビデンスが支えになりにくい場合
当事者にとってのエビデンスは心のささえであるという観点から考えてみます。
セラピストとの相性が大きく影響する手法などは統計的エビデンスが支えになりにくいかもしれません。たとえば、「この悩みを理解できる支援者がなかなかいない」みたいなものとか。
また、自分の新しいストーリーを語るセラピーのように、それをやりたいかどうかで判断した方がよいものもあります。
また、自分の悩みが「○○症」みたいに定型化されていないような場合は、オーダーメイドの心理セラピーになる場合があります。その場合は試行錯誤的なものとなりますので、やってみないとわからないという領域を扱います。統計的エビデンスで選ぶよりも視野が広いセラピストを探すことの方が意味があるかもしれません。
トラウマ分野では、昨今「エビデンスのある心理療法を受ければトラウマが治る。それが普及していないことが問題だ」と信じている支援団体の人が増えていますが、一方でエビデンスのあるプロトコル化された手法ではない関係性重視のカウンセリングやセラピーで良くなっている方が多い実感があります。むしろ、エビデンスのある心理療法でないと助からないと信じていることが問題だと思います。
たしかに、エビデンスのある手法はフラッシュバックなどの「症状」には効果があるのですが、恥や屈辱感、理不尽さ、誰も助けてくれない(ことがある)という事実との折り合いなどは、人との関係性や心理的な安全が重要になります。「症状は治ったけど、トラウマは治っていない」というクライアントが尋ねてきます。
面白いことに、臨床心理学よりもよっぽど科学的な脳神経科学に基づくポリヴェーガル理論でも、手順化どおりに方法にクライアントを合わせようとする作法に警鐘が慣らされています。
現在、さまざまな治療モデルがあるが、どれもエビデンス・ベースドであることが求められている。しかし、これは左脳に偏った思考の産物ではないだろうか。私たちがこのエビデンス・ベースドにこだわり続けていると、目の前のクライアントが展開する、生きた体験を見逃してしまうのではいか、と私は考え始めた。」
『ポリヴェーガル理論臨床応用大全』「5安全こそが治療である」ボニー・バデノック
※引用中の「治療」は医療行為ではなく、広い意味での回復支援を指します。
統計的エビデンスに拘る必要性が低い場合
次のような場合にはエビデンスに拘る必要性は低いかもしれません。
- 成果が主観的であることが大事
- すぐに成果を実感できる実践
- 成果の実感までのコスト(費用や心理負担)が小さい実践
たとえば、「緊張を解くための呼吸法」のようなものは、統計的エビデンスで判断するよりも、やってみる方が早いでしょう。自分がやってみて効果があれば(あるいは効果がなければ)、そちらが自分エビデンスですので、統計的エビデンスに振り回される必要はないでしょう。
一回ごとに成果や価値を納得できるセラピーであれば一回ごとお金をに払ってもリスクはそんなに大きくはないでしょう。
エビデンスがある(けど自分に役立つかはわからない)50万円かけて1年間通うセラピーと、エビデンスはないが説明には納得感があり、やってみてすぐに自分にとって役立つか確認できる1万円のセラピーなら、私は後者を先に試します。
逆にいきなり高額な一括料金や長期間の実践は、エビデンスや事前検証がほしいところです。
目的が「気持ちが楽になって前に進めること」であれば、客観的な尺度を使った調査結果よりも、自分が体験してみて、その自分のニーズを満たしたかどうかを確認すればよいでしょう。
自分エビデンス
これらの場合は、セッション一回ごとに何らかの実感や納得を持てることが重要になります。つまり、最初から自分エビデンスを探す構えってことですね。
ただ、「なんとなくそのときだけラクになる」みたいなのは、それがご自身の目的に適っているか判断が必要です。
そのためには、ご自身が何に実感や納得をしているのか自覚することをお勧めします。
心理セラピーの探索と検証
統計データを見るにしても二つの視点があります。
探索:有益な可能性のあるものを探す
検証:本当に有益かどうか検証する
これはスクリーニングと精密検査にも似ています。スクリーニングとは健康診断で陽性ぽい人を逃さずに拾うことを重視します。
心理実践に当てはめると、探す段階でエビデンスレベルを厳しくしすぎないこと。つまり、信頼できる人の意見のような、低レベルエビデンスも参考にします。これが探索です。
お金や時間をつぎ込むときは高めのエビデンスレベルを求めます。
高めのエビデンスというのは、自分エビデンス、次いで系統的レビュー(複数の学術研究のまとめ)による強い支持です。
お悩みが客観的なものであれば、系統的レビューの範囲だけで探索が成立することもあるかもしれません。