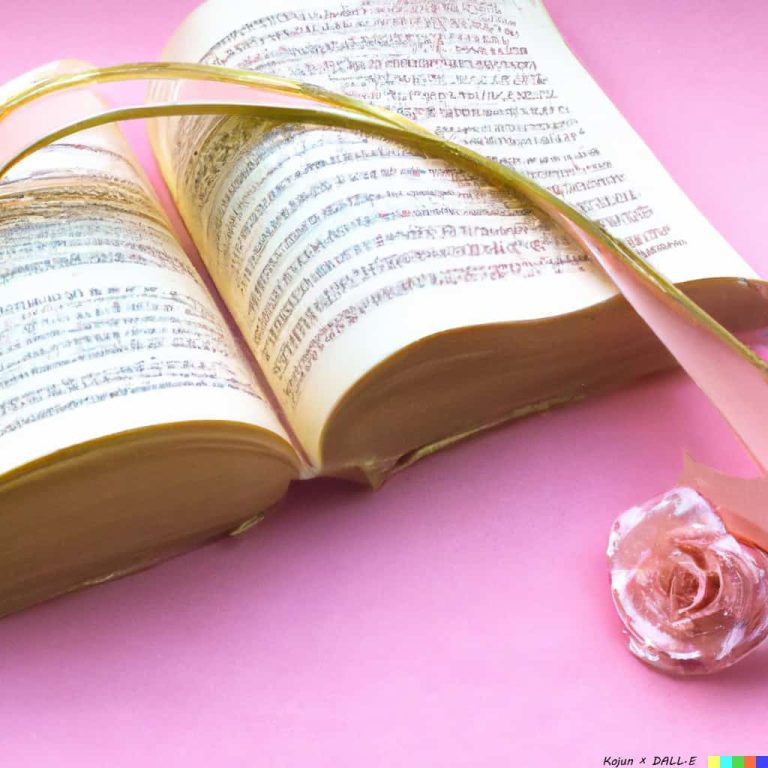「信じられない」という心の病があります。それは幼少期に作られることが多いようです。
「信じられない」病をもつ人は、騙されるのが恐いです。そして、「信じられない」病を解消すると騙されやすくなる、と思っています。
ですが、実際にはそうでもないです。
「信じれない」人の生きづらさ
誰も信じられない人は、相談する相手がいません。信用できる友達もいないし、相談窓口を利用することもできません。人を騙そうとする人にとって、これほど都合のいいカモはいません。
また、何も信じないで生きてゆくというのはとても難しいですから、追い詰められた状況で限られた選択肢から1つだけ選んで頼ることになってしまうわけです。
「なにも信じない」とは言えても、「あなたは信じない」とは言えないのがその病ですから。
何も信じられないということは、追い詰められた選択肢を信じるしかないということでもあるのです。
また、信じないという性質を利用して、支配者の意図と逆の助言をすることによって行動を操ることも出来たりします。
なにが起きているのか
「なんでも信じてしまう」というのも病でしょう。ですが、「信じられない」病を持たないということは、「なんでも信じてしまう」病を持つこととは違います。
「信じられない」病の人はどうやら「いまのところ信じる」とか「おおむね信じる」とかいうことが出来なくなっています。
「いまのところ信じられる」とか「おおむね信じられる」という相談相手を複数もっていれば、騙さそうになったり助けられたりしながらでも生きてゆけます。
そして、疑うという能力も育ちます。
「なにも信じない」というのは「疑う」というスキルを放棄することでもあるので、信じられない人は疑うことが苦手です。
目を閉じて清水の舞台から飛び降りるような信じ方しかできなくなっているのです。
ですから、思い切ってではなくて、おそるおそる信じるというこうとが出来るようになれば克服に近づくでしょう。
克服の鍵
それが考え方の癖のレベルなら認知再構成法(狭義認知行動療法)などで解けるかもしれません。でも、そのようなことはとっくに試したかもしれません。
もっと深いレベルのものであるなら深層心理セラピーで自分の中のなにか「置き去りにされしもの(the left behind)」を癒す必要があるかもしれません。
ですので、「信じられない」病といのは「疑ってはいけない」という病である場合もあります。
「置き去りにされしもの(the left behind)」は、疑うということを許してもらえなかったのかもしれません。
疑ってもいいですよ、ということが心理セラピーの鍵になることもあります。
用心してもいいよってことです。
心理セラピストに対しても疑ってよいわけです。疑えなければ、信じることもできません。
「信じてくれないとできません」という、疑ってはいけないっぽい心理セラピストはこのテーマに向いてないでしょう。
用心して心理セラピストを探してみてください。